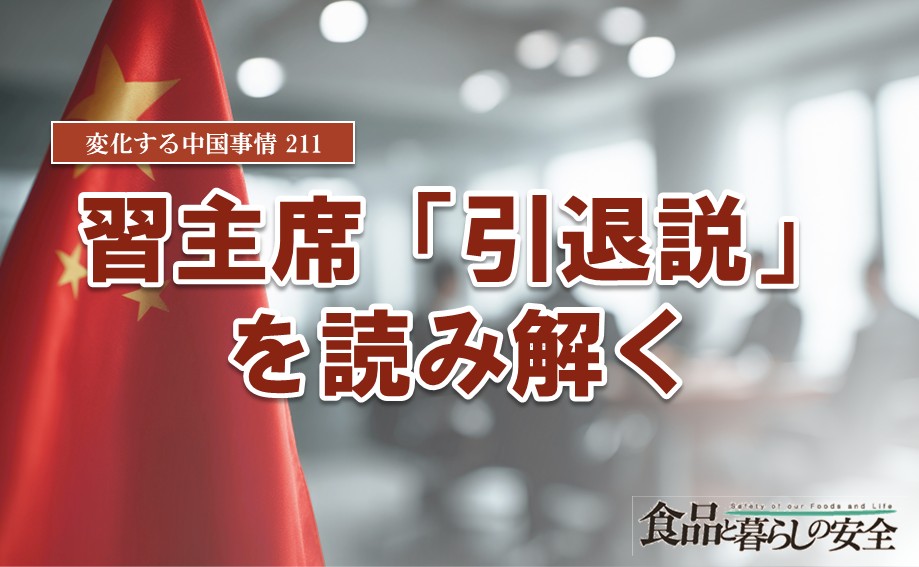中国共産党の最高意志決定機関である中国共産党中央政治局が7月30日、通常通りに今年後半の経済方針を発表した後、四中全会(第4回中央委員会全体会議)の開催を8月から10月に変更したことで「習近平氏、引退か?」と、中国ウォチャーが関心を寄せています。
信じ難い習氏引退説
習近平主席「引退」と聞くと、多くの人が反発するに違いありません。習氏が国家最高の権力者の座に就いたのは、2013年の全人代です。
就任演説で「中華の夢」を語り、「賄賂と汚職」の撲滅を掲げ、14億国民の熱狂的な喝采を浴びていたことが蘇えります。
中国全土に伝播した毛沢東を彷彿させるような庶民の人気と支持を背に、習氏は鄧小平氏が国家体制を健全な形で維持するために定めた最高権力者の任期は「2期10年」の憲法を強引に改正。
現在は3期目の半ばで、4期目どころか“終身 ” 国家主席に留まると観測されるほど強大な権力を持っています。
それだけに、ほとんどの人にとって、「引退」の観測は想定外のことで、信じられないに違いありません。
私も引退説を信じていませんが、これを「憶測」とか「噂に過ぎない」と済ませたら、中国で起こっていることを見誤る可能性が出てくるので、引退説がなぜ出てきているのかを考えてみます。
トップは駆け引きと権力闘争の産物
中国を見るうえで最も大事なことは、誰が“権力”を持っているかということ。
中国の最大の特色は14億の国民を支配しているのは約1億人に達した党員を擁する共産党です。
最高の意思決定機関である中国共産党大会は5年に1度開催され、5年先を見通した政治、経済、軍事、外交など重要課題の方針を決定します。
党大会を補う形で1年に1度、共産党政治局の200名からなる中央委員会全体会議が開催されます。
さらに、毎年3月、中国全土から選ばれたほぼ3000名からなる人民代表が集う全人代(全国人民代表者会議)が開催され、立法する仕組みになっています。
ここで見逃せないことは最高権力者であれ、さらに中央政治局員、全人代議員であれ、選挙で選ばれていないことです。
彼らは党内の「駆け引き」や「権力闘争」を食品と暮らしの安全 2025 年 10 月号(No.438) 11経て生れた妥協の産物なのです。
繰り返すと、中国は民主国家のように地方の村に始まり、国家のトップにいたるまで国民から選挙で選ばれたわけでないから、権力の継承に「正当性」がありません。
だから、権力闘争の渦巻く政局しだいで、アッと言う間に存在が消えてしまう“ 脆い ”立場なのです。
つまり、駆け引きと権力闘争に明け暮れする共産党体制では、異変が勃発するのはごく当然のことです。
ですから、冒頭の「四中全会」の開催期日の変更を切っかけに、「習主席引退か」と憶測されるのは不思議ではありません。
引退説が出る根本理由
ここで考えたいことは、イデオロギー国家の寿命です。中国の兄貴分(老大哥)であったソビエト連邦が崩壊したのは1991年で、1917年の建国から69年後のことです。
ここで多くの政治学者はイデオロギー国家の寿命は「70年が限界」と説きました。
この説で中国共産党を見ると、1949年に建国された新中国は、習近平氏が登場した2013年の段階で、寿命が5年しか残っていなかったのです。
2期目はソ連邦崩壊の69年目に当たる2018年です。
3期目の現在は70年説を遥かに超えています。
しかも、経済成長が中国を民主国家に導くとして新中国を支援してきた米国が、今は巨大な岩盤となって立ちはだかっているのです。
「70年限界説」を別にしても、中国共産党が明らかに「制度疲労」に陥っていることが読み取れます。
国民を支えた経済成長は今や、経済崩壊へと流れを変え、バブルの恩恵を受けた中間層や富裕層は、政府に資産を巻き上げられた暗い時代の再来を恐れ、国外脱出に知恵を絞っています。
底辺の生活から這い上がれなかった農民戸籍を主とする10億に近い庶民は、「明日も仕事があるのか」「会社が存在しているのか」と悩むほど不況に苦しんでいます。
しかし、共産党はこの事態を打破する方策を見い出せません。
この不安から、権力維持を強め、世界最強の「監視システム」強化に一段と邁進しています。
この状況は、共産党の体制が限界に来ている証です。
制度疲労が始まっている
共産党の歴史で驚くことの一つが、毛沢東時代の大躍進政策や文化大革命で数千万人が餓死したにも関わらず、体制が維持されたばかりか、中国全土で体制への疑問が巻き起こらなかったことです。
共産党建国に向けて活躍した20代から40代が防波堤になっていたのです。
しかし、建国から75年を過ぎ、革命世代は完全に消滅し、今や建国どころか、文化大革命も知らないZ世代が主役の時代です。
彼らは、習主席にも国家にも関心を持っていません。
共産党体制は限界なので、習主席が「自ら」引退を考えても、駆け引きで引退に追い込まれても不思議ではないのです。